心房粗動(AFL)は240~440/min で regular の波形をとるマクロリエントリー性頻拍である。有病率としては心房細動(AF)の1/10とされるが、両者は相互に移行することが少なくない。
診断
大多数のAFLは三尖弁を反時計方向に旋回する興奮によって生じる。
「通常型」「非通常型」の用語の意味は日本循環器学会のガイドライン間でも齟齬があり(2020年版の「不整脈薬物治療ガイドライン」と2022年版の「不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン」で異なる使い方をされている)、あまりこだわる意味はないよう。
峡部依存性AFL (CTI-dependent AFL)
三尖弁周囲を旋回するリエントリー回路によって生じるもの。下大静脈-三尖弁輪間解剖学的峡部 (CTI) を回路に含み、CTI-dependent artrial flutter ともよばれる。
反時計方向回旋
AFLの大分部はこの通常型の反時計方向回旋である。すなわち、三尖弁周囲を、心房中隔を上方に、右房自由壁を下方に、250-350/minで回旋する興奮によって生じる。心電図では、下壁肢誘導 II, III, aVF で陰性、V1で陽性、V6で陰性の鋸歯状波 (F波) が現れる。
時計方向回旋
頻度としては稀だが、三尖弁周囲を時計方向に回旋する興奮によって生じるAFLもある。通常と異なり、下壁肢誘導 II, III, aVF で陽性、V1で陰性、V6で陽性のF波がみられる。
峡部非依存性AFL
三尖弁周囲以外の心房内リエントリーによって生じるAFLを非通常型AFLと呼ぶことがある。僧帽弁輪、左房天蓋部、心房筋瘢痕周囲にリエントリー回路ができ、ときに複数が併存する。マクロリエントリー性心房頻拍 (AT) と同機序の不整脈である。
治療
急性期治療
- 心不全・ショック・急性心筋虚血→電気的除細動 (R波同期で 50-100J のカルディオバージョン)
- 血行動態安定→抗不整脈薬 or 電気的除細動による洞調律復帰
抗不整脈薬の選択
峡部依存性AFLでは、周期の約20%が興奮間隙にあたり、解剖学的峡部が相対的伝導遅延部位である。よって、Kチャネル遮断薬で心房筋の不応期を延ばしたり、Naチャネル遮断薬で伝導を抑制したりすることで、AFLの停止を図る。ただし、Kチャネル遮断薬 (e.g. アミオダロン、ニフェラカント) は症候性心房粗動に対しては保険適用が通っていない。
抗不整脈薬投与時には、抗コリン作用によって房室伝導↑、心室拍数↑となって、2:1 – 1:1 の伝導となり、循環不全をきたすおそれがある。よって、事前に非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、β遮断薬、ジギタリス (頻脈への初期対応(病棟)) で房室伝導を抑制しておく。
- I群 (Naチャネル遮断薬) 抗不整脈薬
- ジソピラミド静注
- プロパフェノン経口
- プロカインアミド静注
- フレカイニド静注
- 房室伝導を抑える薬剤
- ジギタリス (IIa C):心血行動態不安定/低心機能のAFLで用いられてきた経緯
- ランジオロール (IIa B):AFLの rate control に有効性が示されているが、AFの場合に比べて有効性が低い。EF<25%、BP<90mmHgの例では未評価である
- 非ジヒドロピリジン系CCB (I A) :AFLの rate control に有効性が示されているが、以下の場合は使用を控える;中等度以上の心不全例。洞機能不全症候群、房室ブロック(ペースメーカー未留置の場合)。心室内伝導障害。WPW症候群などの早期興奮症候群
電気的除細動
薬物治療抵抗例では、経静脈麻酔のうえ、電気的除細動を試みる。
予防的治療
カテーテルアブレーションが第一選択である。希望しない場合、不成功であった場合には、Naチャネル遮断薬、Kチャネル遮断薬などで再発予防を図る。心機能低下例ではβ遮断薬を考慮する。陰性変力作用のないアミオダロンは長期再発予防効果のエビデンスがあるが、日本ではこの使途には未承認である。
抗凝固療法
AFLでもAF同等の血栓塞栓症リスクがあり、急性期・慢性期の抗血栓療法の有効性も示されており、AF同等の管理が推奨される。
参考文献
- 日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン『2022年改訂版 不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン』
- 日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン『2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン』
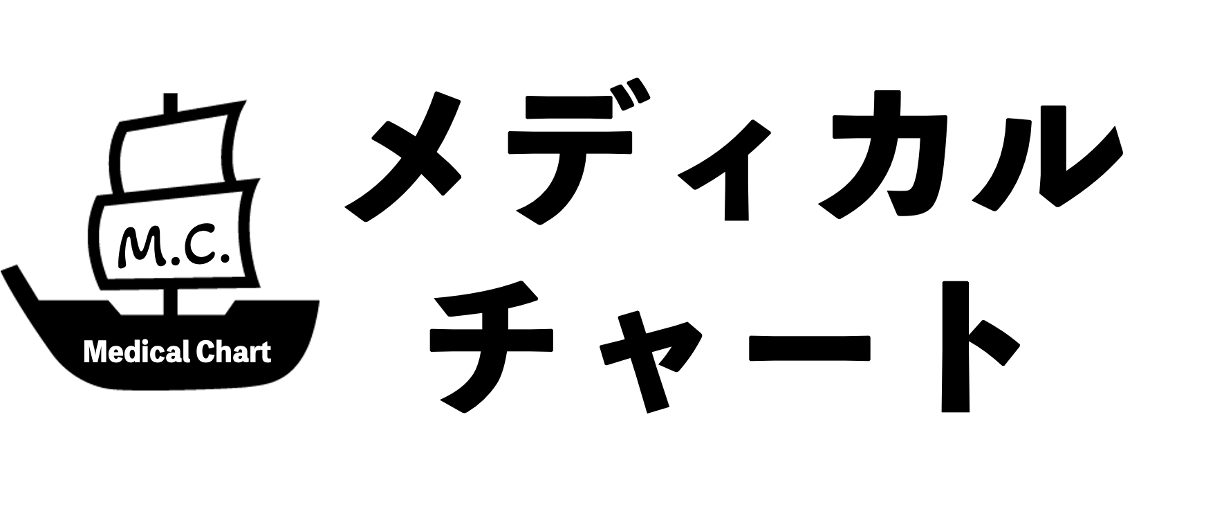
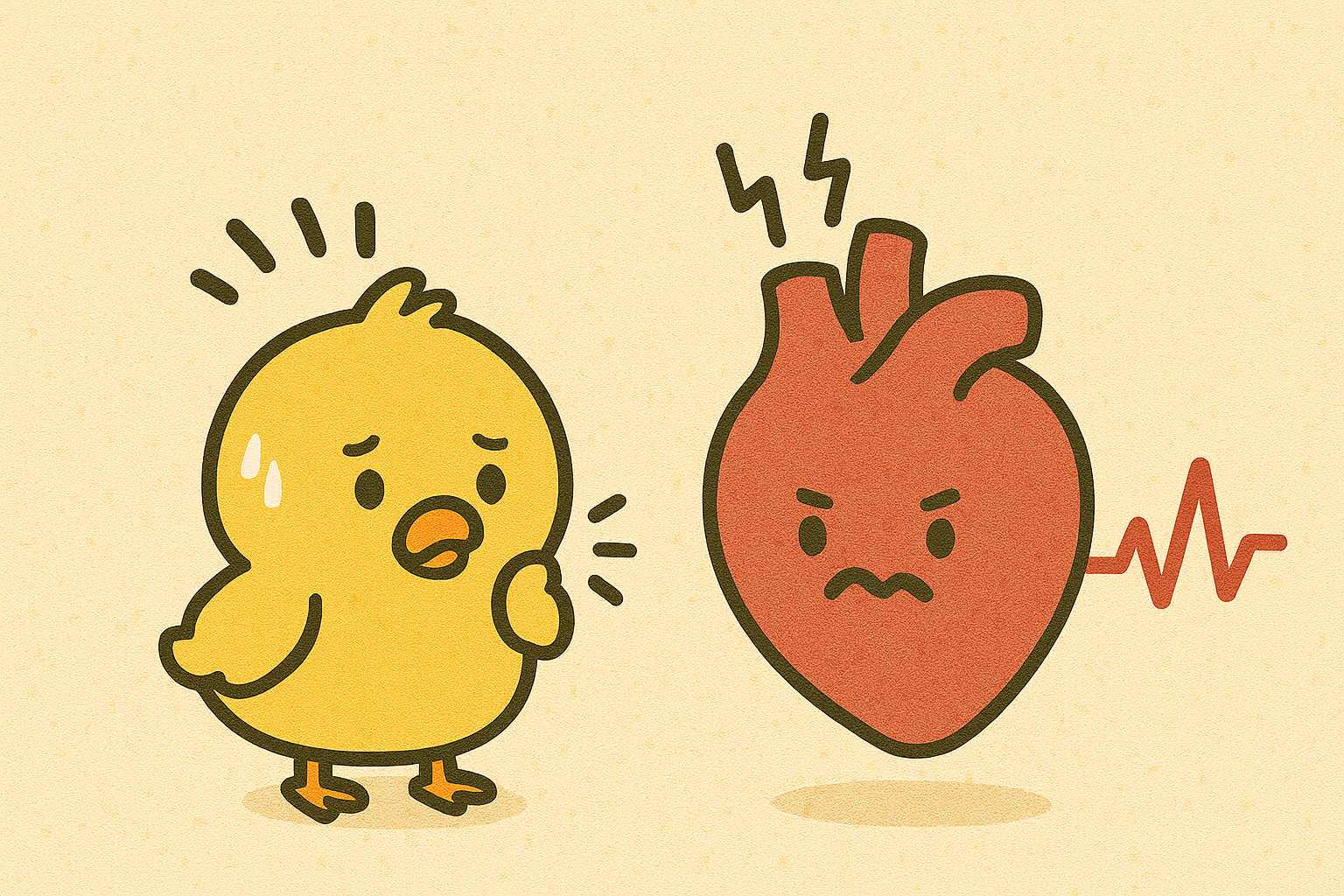

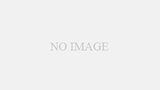
コメント