腎障害を防ぐため、ボリューム不足の補正と尿細管円柱形成の予防を目標として治療を行う。CK値が筋損傷の程度と相関することが知られており、腎障害リスクがあるか否かの判断にCKを用いる。CK > 5000 units/L を閾値とするが、CKがこれから上昇する局面である可能性には注意を要する。通常CKは筋損傷後12時間以内に上昇し、24時間から72時間でピークに達し、5日程度で正常化する。
横紋筋融解症
原因
長時間の筋の圧迫(意識障害、飲酒後など)、多発外傷(交通外傷、地震)、重症熱傷、電撃傷、熱射病、過度の運動、感染(インフルエンザやCOVID-19を含む)、薬物など、原因は様々である。外傷による筋挫滅によるものをクラッシュ症候群と呼ぶ。明確な診断基準はないが、今日の臨床サポートでは、CK≧5~10x正常値を慣習的な目安として記載している。
合併症
急性腎障害が代表的である。循環血漿量低下によるRAA系亢進のため腎血流が低下する、ミオグロビンのヘム鉄からのフリーラジカルが直接の腎毒性をもつ、ミオグロビンと Tamm-Horsfall 蛋白による円柱形性などが機序として考えられている。急性腎障害は横紋筋融解症の10〜50%で生じると考えられている。急性腎障害を合併した場合、死亡率は30%を超える。一概にはいえないが、腎不全の発生率はCKのピーク値と相関することが知られている。
急性腎障害による電解質異常も重大な帰結をもたらしうる。DICやコンパートメント症候群にも注意が必要。
診断
古典的三徴は筋力低下、筋肉痛、褐色尿である。CKの上昇は遅れて現れ、ミオグロビンは腎機能によらずCKより早く代謝されてしまう。よってCKが上がっていなくてもこれから上昇局面に転ずるかもしれないし、尿試験紙法や尿ミオグロビン定性が陰性であることをもって横紋筋融解を否定することはできない。
輸液
晶質液を早期から積極的に投与することで、腎血流を維持・増強して虚血性の損傷を防ぐとともに、尿流を増やして尿細管内のヘムの濃度を下げて円柱形成を防ぎ、閉塞を洗い流す、というコンセプト。災害時などの外傷契機の横紋筋融解症において、発症早期からの大量輸液で腎不全発症率を抑えられるとの報告がある。
下記の通り、かなりアグレッシブに多量の輸液を投与する。このプロトコルの根拠の多くは災害時などの外傷による筋損傷における研究がもととなっており、エビデンスとしては確たるものではない。
輸液製剤の種類
輸液は通常、生理食塩水を用いる。Cl制限の要否は明らかになっていない。UpToDate の記載では、高K血症が問題となることが多いため、K含有の輸液は避けたほうがよいとされている。今日の臨床サポートでは、細胞外液であれば種類は問わないものとされている。
輸液の速度
筋損傷・横紋筋融解や溶血を認知した後、可及的速やかに生理食塩液を投与する。
横紋筋融解症では損傷した筋の中に体液が閉じ込められてしまうため、溶血の場合より多量の輸液を要する。したがって、横紋筋融解症に対しては生理食塩液 1〜2 L/h、溶血に対しては 100〜200 mL/h (重症では 200〜300 mL/h) 程度の速度で開始する。
その後、ボリュームと尿量を見ながら輸液を調節する。ボリュームが十分かつ尿がある場合、尿量 200〜300 mL/h となるよう輸液を絞る。十分な輸液(横紋筋融解症で6L、溶血で3Lなど)にもかかわらず尿が少量しか得られない場合、循環の補助に必要なだけの量まで輸液を絞る。Volume overload の所見がみられた場合には、輸液は中止する。
Volume overload の所見がない限り、横紋筋融解症では、CK ≦ 5000 U/L かつ低下傾向となるまで輸液を継続する(peak CK < 5000-10,000 ではAKIは起こりづらいとのデータあり)。溶血の場合は、LDH < 1.5x基準範囲上限 となり、Hb が6時間以上安定するまで輸液を継続する(エビデンスには乏しい)。
マンニトール、重炭酸
重篤な場合で、低Ca血症がなく、血ガスでpH<7.5、HCO3-<30 mEq/L である場合には、重炭酸の投与を検討する。エビデンスには乏しくルーチンでは使用しない。
- 今日の臨床サポート
- メイロン静注液 (8.4%) 50 mL + 5%ブドウ糖液 500mL を 200 mL/h で投与し、尿pH>6.5 を目標に管理する
- 20%マンニットール注射液を 0.1 g/kg/h で開始し尿量を確保できるよう調整する。1日量は200 g 以内にとどめる
ループ利尿薬
横紋筋融解症に対して特異的に調べた研究はないよう。重症患者の急性腎不全においては、ループ利尿薬によって尿量は確保できるが予後は改善しないとの報告がある。研究によってはループ利尿薬投与群のほうが死亡率・非代償性腎不全合併率が高かったものもある。
したがって、原則としてルーチンでの使用は推奨されない。循環血漿量を確保できている状態で、K低下・アシドーシス改善などを意図して用いる場合はある。
腎代替療法
はっきりしたエビデンスはなく、AKIとして要否を判断する。
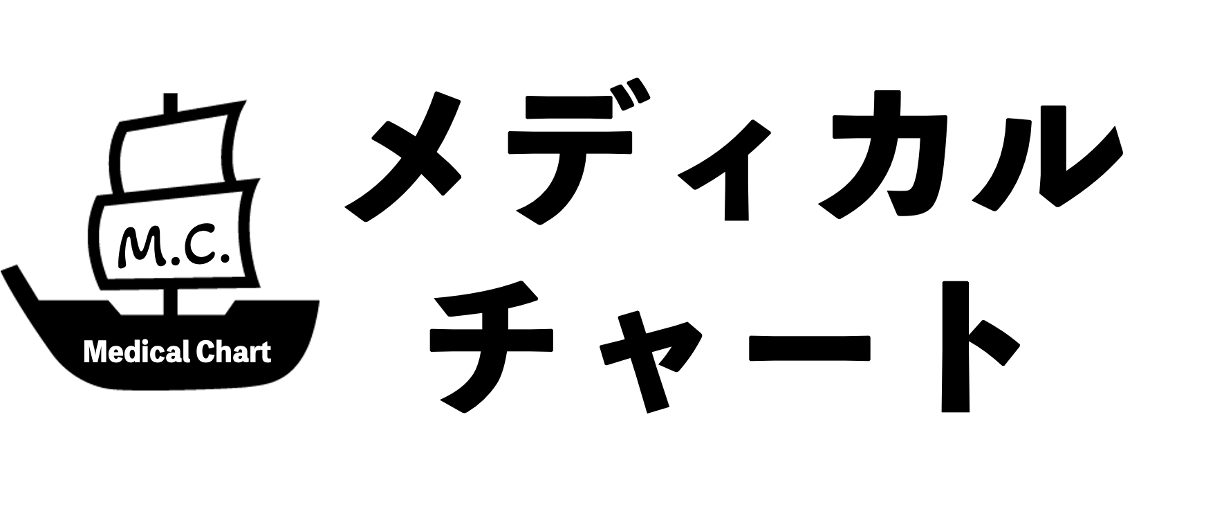

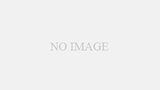

コメント