PE、DVTに対する抗凝固療法について、2025ガイドラインをもとに整理する。
PE・DVTの治療の原則
PTEや中枢型DVTは、重篤でなく禁忌がなければDOACを用い、最低3ヶ月治療する。末梢型DVTは経過観察する。
肺血栓塞栓症
- ヘパリン (目標:APTT が対照値の1.5~2.5倍) 等の非経口抗凝固薬を開始し、ワルファリンを併用する。ヘパリン等はワルファリンが治療域 (PT-INR 1.5~2.5) に達するまで継続する。
- 血行動態が安定している場合は DOAC を投与する。エドキサバンは適切な初期治療後に開始する。リバーロキサバン・アピキサバンは高用量の初期強化療法をまず行う。
- 最低3ヶ月間の治療を行い、その後の抗凝固継続要否は再発・出血リスクと臨床的な重大性を加味して判断する
中枢型DVT(膝窩静脈とそれより中枢側)
- ヘパリン (目標:APTT が対照値の1.5~2.5倍) 等の非経口抗凝固薬を開始し、ワルファリンを併用する。ヘパリン等はワルファリンが治療域 (PT-INR 1.5~2.5) に達するまで継続する(IB)
- DOAC を投与する。エドキサバンは適切な初期治療後に開始する。リバーロキサバン・アピキサバンは高用量の初期強化療法をまず行う(IA)
- 最低3ヶ月間の治療を行い、その後の抗凝固継続要否は再発・出血リスクと臨床的な重大性を加味して判断する。ただし、活動性がん患者の中枢性DVTについては、がんの活動性がある限り抗凝固療法を継続する。
末梢型DVT(膝窩静脈より末梢側)
- 必ずしも抗凝固療法は要さない。理学療法を行い、中枢進展しないか観察する。
- 抗凝固療法を行う場合でも3ヶ月までとする。活動性がん合併の場合は3ヶ月以上の延長治療も視野には入る。
- DOAC の RCT では末梢型DVTが除外されたためエビデンスは不十分。
- 症候性末梢型DVTは2週間以内に伸展がなければそれ以上伸展しない。無症候性DVTの自然予後は良好。
- 7〜14日後にエコー再検で中枢伸展がないか確認し、伸展例や再発の高リスク症例のみに抗凝固療法を行う。リスクは、症候性、膝窩静脈近くの大きな新鮮血栓、活動性がん、VTE既往、周術期、入院など。
抗凝固療法各論
未分画ヘパリン
静脈注射または皮下注射する。迅速に抗凝固効果を与え、硫酸プロタミンで速やかに中和できる。
フォンダパリヌクス(アリクストラ)
合成ペンタサッカライド間接的Xa阻害薬。皮下注射。PE患者において、VTE再発、出血性合併症、死亡率が未分画ヘパリンと同等であること、DVT患者において、VTE再発率、出血性合併症発症率、死亡率が低分子ヘパリンと同等であることが示されている。作用の個人差が少なくモニタリング不要であるため使いやすいとのこと。
ワルファリン
ビタミンK依存性凝固因子である II, VII, IX, X の合成を抑制する。投与初期にプロテインC、プロテインSの合成を抑制することで凝固作用がいっとき亢進しうる。また、治療域にコントロールをつけるまでに多少の時間がかかる。したがって、初期には未分画ヘパリンやフォンダパリヌクスを用いる必要があり、はじめからワルファリン単剤とすることは推奨されない。
欧米では通常 PT-INR 2.0~3.0 でコントロールされるが、日本では慣習的に 1.5~2.5 を指標とする。
DOAC
ヘパリンやワルファリンに比して、VTE再発が非劣性で、出血性合併症が少ない可能性がある。アジア人は概して抗凝固療法による出血リスクが高い傾向にあるが、ワルファリンに比したDOACの安全性がアジア人で特に目立つ可能性も指摘されている。ただし、
- 高度腎機能低下例には使用できない
- 重症例ではエビデンスが乏しい(各RCTで除外されている)
- 抗リン脂質抗体症候群では有効性・安全性ともワルファリンに劣る
| リバーロキサバン (イグザレルト) | アピキサバン (エリキュース) | エドキサバン (リクシアナ) | |
| 臨床試験での投与方法 | 15 mg x2/日 3週間 → 15 mg x1/日 | 10 mg x2/日 1週間 → 5 mg x2/日 | ヘパリン投与後 60 mg または 30 mg x1/日 |
| 対照薬 | エノキサパリン / ワルファリン | エノキサパリン / ワルファリン | ヘパリン / ワルファリン |
| VTE再発±関連死 | VTE再発に非劣性 | VTE再発/関連死に非劣性 | VTE再発に非劣性 |
| 出血性合併症 | 非劣性 | 優越性 | 優越性 |
| メモ | ・3週間経過後は1日1回にできる | ・2日2回の投与を要する | ・適切な初期治療後に使用する ・体重やCCrによる減量基準がある1,2 |
筆者メモ:
・DOACのみで治療 → イグザレルト、エリキュース
・出血合併症が気になる → エリキュース、リクシアナ
・1日1回にしたい → イグザレルト、リクシアナ
・CCr 15~30 → リクシアナしか使えない(ほかは禁忌)
抗凝固療法の継続期間
最低3ヶ月間の抗凝固療法が必要
ワルファリンに基づく研究では、
- 最低3ヶ月の抗凝固療法が必要
- 抗凝固療法の期間を3〜6ヶ月におさえても、12〜24ヶ月投与しても、抗凝固療法終了後のVTE再発リスクは変わらない
- 抗凝固療法を>3ヶ月続けるとVTE再発リスクは下がるが、出血リスクは増大する可能性がある
DOAC であればワルファリンより出血リスク増加が抑えられる可能性があり、国際ガイドラインではより長期の抗凝固療法継続が推奨されているようである。特に、リバーロキサバン 10 mg やアピキサバン 2.5 mg x2 といった低用量DOACの有用性が示唆されているが、日本では保険適応がない。
つまるところ、抗凝固療法後の再発リスク、出血リスク、重大性(PTEか否かなど)を推定し、>3ヶ月の抗凝固の有益性とリスクを比較する必要がある。
VTE再発のリスク
誘引の有無
- 一過性 (transient) の要因がある:外科手術など。誘引解除後は再発リスクは低い
- 誘引がない (unprovoked):中間程度
- 持続性 (persistent) の要因がある:活動性のがんなど。再発リスクは高い
付加的な危険因子
- 高齢、男性:報告は一定せず強力とはいいがたい
- 肥満:VTE発症のリスクだが、再発リスクかは不詳
- 血栓部位:PTE>中枢型DVT>下腿型DVT4
- 再発例
- 残存血栓
- 治療終了1ヶ月後のD-dimer高値:高齢などを背景に軽度高値を示しうることの注意
抗血小板療法による代替
抗血小板作用をもつアスピリンは、VTE予防効果は抗凝固薬に劣るが、出血リスクが低く、整形外科術後VTE予防にはエビデンスがある。抗凝固療法が困難である場合にはアスピリンを検討可能である。
抗凝固療法開始後の安静度
- 2025ガイドラインでは抗凝固療法開始後速やかに安静を解除することが推奨されている
- 他方、その根拠とされているメタアナリシスをたどると5、ほとんどの研究で介入は低分子ヘパリン+ワルファリンであり、DOACを用いたものは(少なくとも明示的には)ない。確かに多くの研究では day 0 で安静を解除しているようだが、それはヘパリンの iv などで速やかに抗凝固を導入した場合であろう。DOACを用いた場合にどの時点で十分に抗凝固が効いたと判断すべきなのかは不明である。
参考文献
- 2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf
- ① 体重≦60kg, ② Car 30-50 mL/min, ③ P糖蛋白阻害効果のある薬と併用 の場合は 30 mg/日 ↩︎
- CCr 15-30 mL/min では添付文書上 30 mg/日を投与可能だが、安全性・有効性は確立していない ↩︎
- 2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf ↩︎
- 再発時に同一部位・同一疾患になりやすいという報告がある。ガイドライン脚注30から孫引き。 ↩︎
- https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121388 のみ本文を閲覧可能であった。ほか2つはより古い研究であり、DOACが解析対象に入っていることはおそらくない。 ↩︎
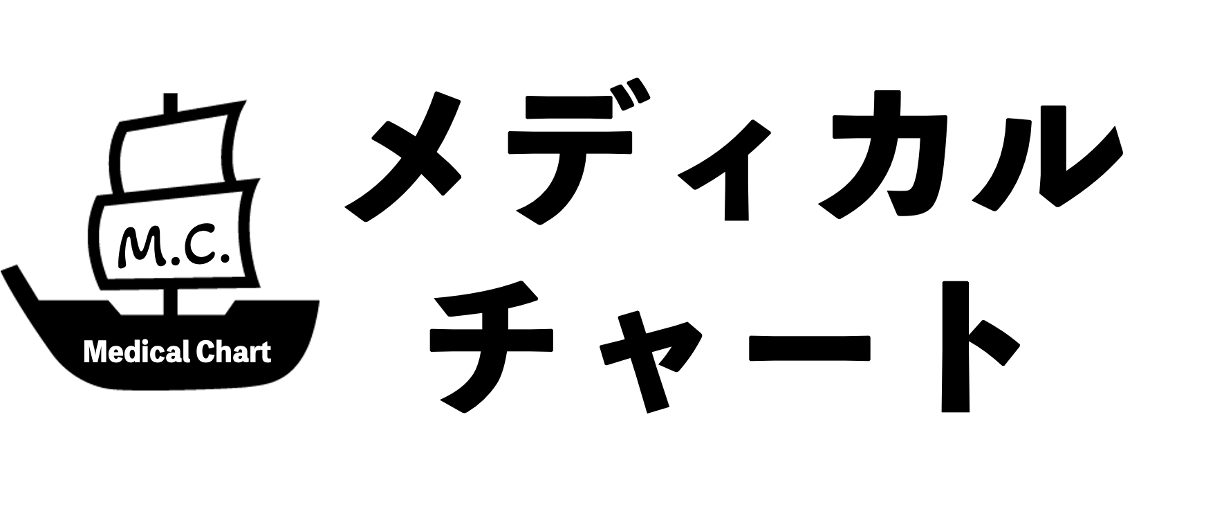

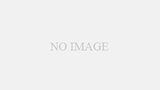
コメント