疑ったら
- 心電図
- 血液ガス
- (再検指示)
介入の判断
- K > 6.0 mEq/L
- 心電図変化あり(テントT→P波消失→wide QRS)
の場合は緊急で治療介入する。
ただし、K値の急激な上昇と慢性的な高値ではリスクが異なることに留意。
直ちに行う応急処置(グルコン酸カルシウム)
- グルコン酸カルシウム投与
- カルチコール 10mL/1A 1Aを2~5分かけてゆっくり静注(内科レジデントの鉄則)
- カルチコール 10~20 mL 静注(内科診療ことはじめ)
- カルチコール 10mL 3~5分で静注(レジデントのためのこれだけ輸液)
- カルチコール 20mL 2~5分かけて投与
ジギタリス内服中:カルチコール 10mL + 5%ブドウ糖液 100mL 20~30分かけて投与
(救急外来 ただいま診断中!)
最初の治療(GI療法)
組成に定まったものはない。基本的にブドウ糖 5g の代謝に K 1mEq, インスリン 1単位が必要と考えられており(5:1:1の法則)、GI療法ではこれよりインスリンの比率を増やした組成とするのが通常である(救急外来 ただいま診断中!)。ただし、GI療法におけるK低減効果はインスリンの量ではなくブドウ糖の量に依存する(同前、孫引き)。
インスリンは速攻型のヒューマリンRまたはノボリンRを用いる。
- インスリン 10単位 + 50%ブドウ糖液 50mL を10分かけて静注(レジデントのためのこれだけ輸液)
- インスリン 8単位 + 50%ブドウ糖液 40mL(救急外来 ただいま診断中!)
- インスリン 4〜10単位 + 50%ブドウ糖液 40mL 静注
インスリン 10単位 + 10%ブドウ糖液 500 mL 点滴静注(内科診療ことはじめ) - インスリン 5単位 + 50%ブドウ糖液 40mL 1~2分かけてゆっくり静注(内科レジデントの鉄則)
次に行う治療(利尿、β刺激薬、イオン交換樹脂)
β2受容体刺激薬
点滴ライン不要であり簡便。冠動脈疾患の患者では禁忌。
- 塩酸プロカテロール(メプチン)または硫酸サルブタモール(ベネトリン)をネブライザーで吸入
- ベネトリン吸入液 0.5% 2mL (サルブタモールとして10mg)吸入(救急外来 ただいま診断中!)
- サルブタモール(ベネトリン)10mg (2 mL) + 生理食塩水 吸入(内科レジデントの鉄則)
- 上記は喘息への投与量の約4倍で、喘息に準じた量を投与することもある(同上)
利尿薬
フロセミド(ラシックス)を投与する。ただし、自尿のない透析患者では無効である。原疾患が腎前性腎障害であれば逆効果。
- フロセミド(ラシックス)20〜40 mg 静注(救急外来 ただいま診断中!)
- フロセミド(ラシックス)20〜100 mg 静注(内科レジデントの鉄則)
陽イオン交換樹脂
古典的にはカリメート、ケイキサレート。最近はロケルマ。基本的には発現時間が遅く、救急外来で投与するものではない。ロケルマは例外かもしれないが、添付文書上はやはり緊急時の使用はすすめられない。
血液透析
維持透析患者、透析間際のCKD患者、以上の治療に反応しない患者は基本的に透析が必要。
輸液の選択
生理食塩水はそれそのものはKを含まないが、高Cl性代謝性アシドーシスによるK上昇のリスクがある。他方、乳酸リンゲル液(ラクテック)などの頻用される晶質液はKを含むが、乳酸や酢酸などの緩衝作用のある成分を含んでおり、アシドーシスによるKの細胞外移行を阻止しうる。
高K患者・AKI患者を対象とした最近の研究では、生理食塩水と晶質液とで高Kのリスクは変わらず、腎代替療法への移行は晶質液のほうが少なかった(https://doi.org/10.1164/rccm.202011-4122le)。
上記文献を引き、坂本は「大量の輸液が必要な場合には、生理食塩水ではなくリンゲル液を使用」することを推奨している(救急外来 ただいま診断中!)。
維持透析患者でどうしてもKを投与したくない場合は、病院の風土によっては、1号液でライン確保するのも手かもしれない(私見)。
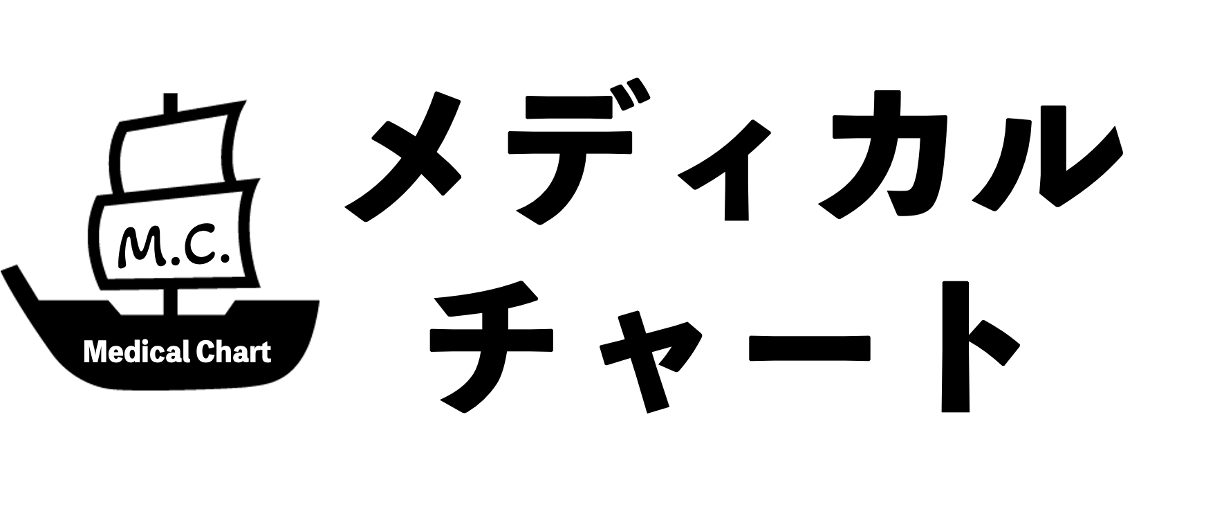

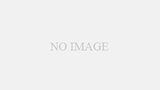
コメント