不安定な頻脈を除外する
内科救急の原則通り、1st impression (1次ABCD評価) を確認する。ABCDに異常がある場合、呼吸困難や胸痛がある場合は不安定な頻脈と判断し、循環器 call のうえ、カルディオバージョンを考慮する。
通常不安定になるのはVTやVFだが、心機能低下例では上室性頻脈でも不安定化し得、カルディオバージョンの適応となる。
※pulseless VT や VF はACLSに移行!
1st impression を評価する流れで、"OMI", "ABCD" を見る
12誘導心電図で頻脈の種類を判断する
narrow vs wide, regular vs irregular の2軸で大まかに分類する。
- narrow QRS regular tachycardia
- 洞性頻脈
- 上室性頻脈 SVT (AVRT, AVNRT, AT/AFL)
- narrow QRS irregular tachycardia
- 心房細動 AF
- wide QRS regular tachycardia
- 心室頻拍 VT
- SVT + 伝導障害
- wide QRS irregular tachycardia
- 心室細動 VF
- Torsade de pointes
- AF + 伝導障害
洞性頻脈の場合
洞性頻脈は需要増加に対する代償の場合があり、投薬によって脈拍を直接に下げてはいけない。原因を調べ、それを治療する。なお、一般に洞性頻脈は「220-年齢」を超えないとされ、それを超える頻脈では洞性頻脈以外を疑うべきである。
頻脈の語呂合わせ “TACHY”
- Thyroid, Toxin:甲状腺機能亢進、中毒
- Anemia, Alcohol, Acidosis, Ache:貧血、アルコール離脱、アシドーシス、疼痛
- Cardio:心不全、虚血、肺塞栓
- Hypoxia, Hypovolemia, Hypoglycemia, Heat:低酸素血症、脱水、低血糖、発熱
- 「さるも聴診が好き(超音波、心電図、胸部写真、血液ガス)」に採血と血糖を追加
- 血液検査:血算, 生化学 (TSH, FT4含む), 血糖
- 血液ガス
- 心エコー:vEF, IVC
- 胸部X線写真
- 簡易血糖測定
心房細動 AF の場合
発症7日以内の発作性心房細動で、バイタルが安定している場合は、経過観察でもよい。不安定な場合は、まずはレートコントロールを行う。
0. 血行動態が破綻している場合
100Jの電気的除細動を行う
1. 原因の検索と解消
洞性頻脈同様に、頻脈の原因を検索する。脱水であれば輸液負荷だけでもレートコントロールを得られる可能性がある。
頻脈の語呂合わせ “TACHY”
- Thyroid, Toxin:甲状腺機能亢進、中毒
- Anemia, Alcohol, Acidosis, Ache:貧血、アルコール離脱、アシドーシス、疼痛
- Cardio:心不全、虚血、肺塞栓
- Hypoxia, Hypovolemia, Hypoglycemia, Heat:低酸素血症、脱水、低血糖、発熱
- 「さるも聴診が好き(超音波、心電図、胸部写真、血液ガス)」+採血, 血糖
- 血液検査:血算, 生化学 (TSH, FT4含む), 血糖
- 血液ガス
- 心エコー:vEF, IVC
- 胸部X線写真
- 簡易血糖測定
2. レートコントロール
HR < 110/min を目標とする1。1. で明らかな誘引を特定できなかった場合や、誘引に対応(脱水→補液など)してもレートコントロールを得られなかった場合は、薬剤によりレートコントロールを図る。主たる武器は、Ca拮抗薬、β遮断薬、ジゴキシン。心機能、内服可否などを考えて選択する。
EF > 40%
Ca拮抗薬もβ遮断薬も使える。薬を飲めるなら以下どれでも使える。飲めないなら、ワソランやヘルベッサーを点滴するか、ビソノテープを貼るかのどちらか。オノアクトを使ってもよいだろうが、高価だし、保険適応上の問題がある。ビソプロロールは経口もテープ製剤(ビソノテープ)もあり、薬を飲めない例でも使えるので扱いやすい(私見)。ただし、テープ製剤の血中濃度の立ち上がりは経口薬には劣ることに留意2。
- 非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬
- ベラパミル(ワソラン)5 mg/A, 1A = 2 mL
- ベラパミル 1A + 生食 50 mL 15~30分かけて点滴静注(内科診療ことはじめ)
- ベラパミル 1A + 生食 8 mL (= 10 mL) を調製し、2 mL (1 mg) を静注。10分で効果判定し、不十分なら追加で 2~4 mg 静注する(内科レジデントの鉄則)
- ベラパミル 1回 40~80 mg 1日3回 経口投与(内科レジデントの鉄則)
- ジルチアゼム(ヘルベッサー)
- ジルチアゼム 3V (50mg/V) + 生食 50mL を 2mL/h から開始(内科診療ことはじめ)
- ジルチアゼム 10 mg + 生食 50 mL を約3分間で緩徐に静注(内科レジデントの鉄則)
- ジルチアゼム 1回 30~60 mg 1日3回 経口投与(内科レジデントの鉄則)
- ベラパミル(ワソラン)5 mg/A, 1A = 2 mL
- β遮断薬
- ビソプロロール(メインテート)
- ビソプロロール 0.625 mg 1日1回 経口投与。最大 5 mg/日(内科診療ことはじめ)
- ビソノテープ (ビソノテープ 1mg ≒ ビソプロロール経口 0.625 mg)
- カルベジロール(アーチスト)
- カルベジロール 1回 1.25 mg 1日1~2回 経口投与。最大 20 mg/回(内科レジデントの鉄則)
- メトプロロール(セロケン)
- ビソプロロール(メインテート)
EF < 40%
Ca拮抗薬が使えない。残る武器はβ遮断薬、ジゴキシン。急性期で細かに調節したいなら、ランジオロール持続静注を選ばざるを得ない。
- ランジオロール(オノアクト)
- ランジオロール 50~150 mg + 生食 50 mL。1γから持続投与(内科レジデントの鉄則)。効果発現・消失とも早く、使いやすい。血圧低下を起こさないわけではないので注意。1850円/50mg、4848円/150mg と比較的高価な薬剤である。
- ジゴキシン(ジゴシン)
- ジゴキシン 0.25 mg (1A) を緩徐に静注するか、生食 50 mL に希釈して点滴静注する(内科レジデントの鉄則)。使用前に腎機能障害、WPW症候群の有無を確認する。作用発現までに15〜30分かかる。
- アミオダロン(アンカロン)
3. 抗凝固療法
心房細動は発作性であっても永続性であっても抗凝固療法の適応であり、血栓塞栓症のリスクを2/3程度まで下げられる。日本のガイドラインはCHADS2スコアを採用しており、chronic heart failure, hypertension, age≧75y/o, diabetes mellitus, stroke or TIA (2点) で1点以上となるか、0点でもその他のリスクに該当するなら、DOACが推奨される。
ただし、敗血症などの急性疾患に伴う心房細動に対する抗凝固療法の効果は未証明で、出血合併症が増える可能性がある(Walkey AJ, et al. JAMA Cardiol. PMID: 27487456. 内科診療ことはじめより孫引き)。
発作性上室性頻拍 PSVT の場合
修正バルサルバ法、ATP急速静注を試みる。それでもだめなら非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬であるベラパミル(ワソラン)、ジルチアゼム(ヘルベッサー)を試みる。
根治的にはカテーテルアブレーションの適応があるが、発作が短く症状が軽い場合には抗不整脈薬頓用で対応する場合がある。その際、WPW症候群がなければ房室伝導を抑制する薬剤を、WPW症候群があればその他の抗不整脈薬を使用する。
上室性の頻脈(PSVTやAF)のレートコントロールには、房室伝導を抑制する薬剤を用いる。主には、非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、β遮断薬をおさえておく。ATPも投与の意図はやはり房室伝導の遮断である。
Ca拮抗薬のうち非ジヒドロピリジン系に属するベラパミル(ワソラン)、ジルチアゼム(ヘルベッサー)は、房室結節に作用して心拍数を抑える (rate control)3。β遮断薬(プロプラノロール(インデラル)、ランジオロール(オノアクト))もまた房室結節を抑制して心拍数を減少させる。PSVTの診断・治療に用いられるATPだが、やはり房室伝導を遮断することで異常な回路の伝導を止めることを意図している。
心室性不整脈の場合
- VF → ACLS。ただちに胸骨圧迫+除細動
- pulseless VT → ACLS。ただちに胸骨圧迫+除細動
血圧の維持されているVTの場合、人を集め、循環器コールする。循環が不安定なら迷わずカルディオバージョンする。
原因検索
電解質異常、虚血性心疾患の検索が必要である。血液検査、12誘導心電図、心エコーを検討する。Torsades de pointes をきたすような薬歴がないかも確かめる。
心室性不整脈に用いる薬剤
- アミオダロン(アンカロン)125 mg + 5% Glucose 100mL。10分かけて投与(内科レジデントの鉄則)
- リドカイン(キシロカイン)100 mg (1A 5mL) のうち 2.5 mL を生理食塩水で希釈し、2分以上かけて投与(内科レジデントの鉄則)
参考文献
脚注
- 心拍数が110/minを超えていると頻脈誘発性心筋症を生じる可能性があるため。 ↩︎
- https://med.toaeiyo.co.jp/contents/tape-manual/tape-manual03.html ↩︎
- 降圧目的に頻用されるアムロジピン、ニカルジピン、ニフェジピンはジヒドロピリジン系で、血管平滑筋に作用する。 ↩︎
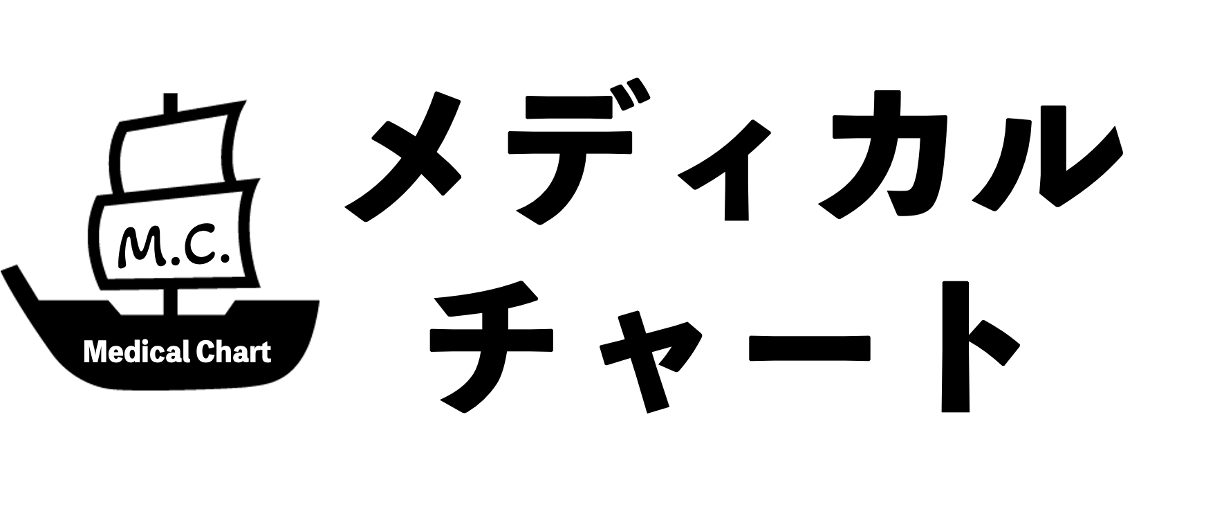
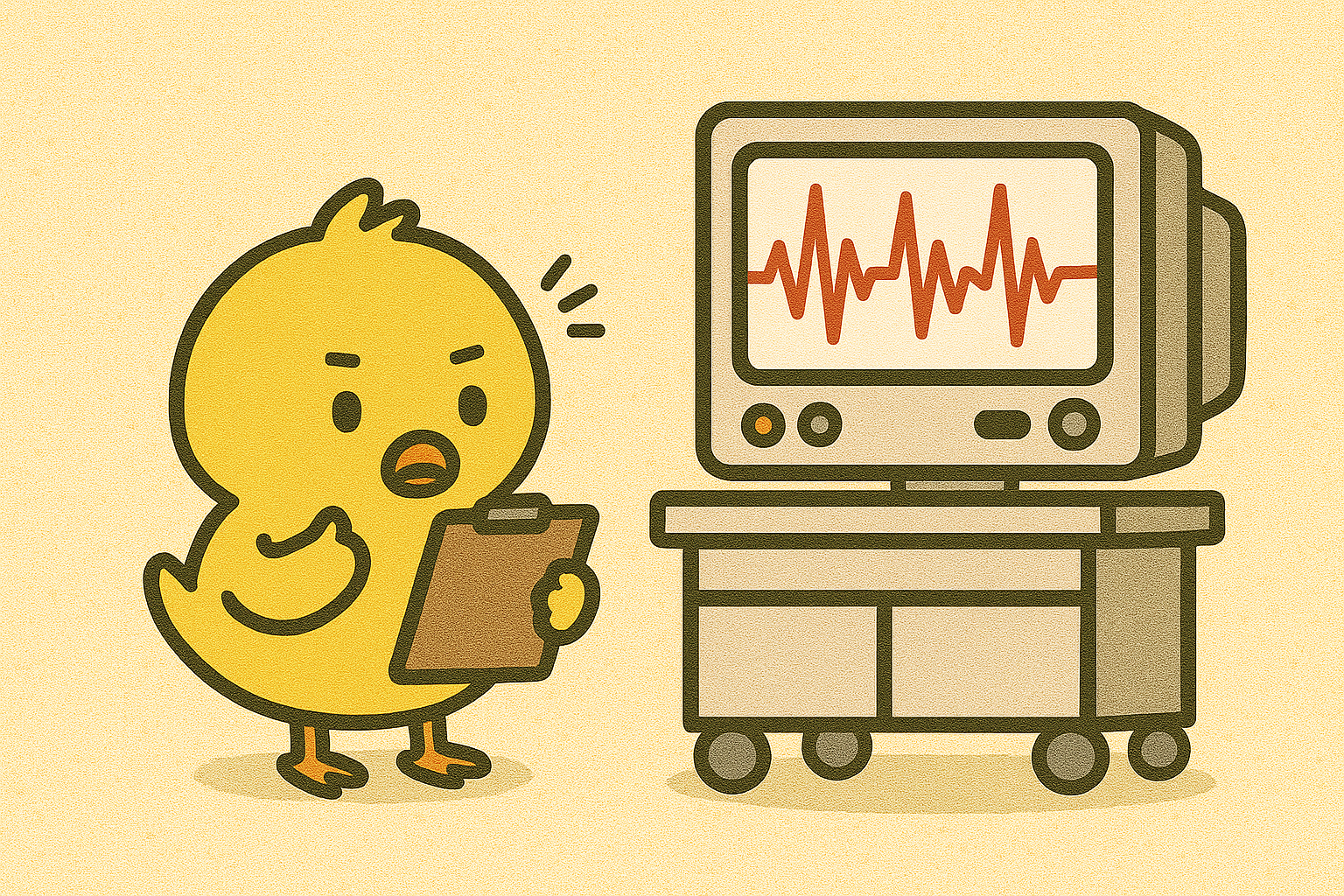


コメント