基本的には珍しい疾患とされており、4年間にERを受診した約25万人の患者のうち、0.007%にあたる17人のみが急性腎梗塞と診断されたと報告されている。他方、腎梗塞を尿路結石や腎盂腎炎と鑑別することは容易ではなく、見逃しや診断の遅れが生じやすい疾患であり、実際の有病率はより高いものと考えられる。
原因
心原性塞栓
急性腎梗塞患者438例の研究では、55.7% が心原性塞栓によるもので、そのほとんどが心房細動であった。ほかに、心筋症、心内膜炎に加え、大動脈のアテロームに由来する塞栓も報告されている。
一般に知られる通り、AFは血栓塞栓症のリスクである。腎梗塞はAFの初発症状でもあり得る。また、すでに診断のついているAF患者に腎梗塞が生じた場合、その多くはワルファリンの投与量が不十分である。
腎動脈の損傷
上記の研究で、腎梗塞例の33%には、腎動脈解離、外傷、マルファン症候群、結節性多発動脈炎を背景とする動脈損傷があった。
過凝固状態
腎梗塞例の6.6%は hereditary thrombophilia や高ホモシステイン血症、抗リン脂質抗体症候群、ネフローゼ症候群などの過凝固状態にあった。COVID-19との関連の報告もある。避妊用ピル内服者にも生じうる。
特発性
上記研究で、30.1% は原因が同定されなかった。
臨床像
症状
急性発症の側腹部・腹部痛に嘔気・嘔吐や発熱を伴う。ときに急性の血圧上昇がみられる。無症候性の例もあり、画像検査で偶発的に発見される。
- 側腹部痛 50%
- 腹痛 53%
- 嘔気 17%
- 嘔吐 13%
- 発熱 10%
検査所見
- 血尿 32%
- 蛋白尿 12%
- Cre 平均 1.0 mg/dL (0.4-5.6 mg/dL)
- LDH↑ (平均 656 IU/L, 152-7660 IU/L)
- WBC, CRP の上昇
基準値上限の2-4倍以上の著明なLDH上昇があり、アミノトランスフェラーゼの上昇がごく軽微であれば、腎梗塞が強く示唆される。このような検査異常パターンは、時間のたった心筋梗塞、溶血、腎移植後の拒絶反応などでみられうるが、通常腎梗塞との鑑別は容易である。
診断
腎梗塞の症状は非特異的で、迅速に診断される例は半分未満である。急性発症の側腹部・腹部痛が塞栓症リスクのある患者に生じた場合、腎疝痛1や腎盂腎炎と診断されたが他の疾患を除外しきれない場合に腎梗塞を疑う。
検討するべき検査
- 血算(分画を含む)
- 血清Cre、LDH
- 尿沈渣、尿培養
- 心電図(AF評価)
- 造影CT、または造影MRI
画像検査の感度
ラジオアイソトープは近年はあまり使われない。造影CTが診断のゴールドスタンダードである。腎梗塞に関しては、超音波検査は感度が低い。
- ラジオアイソトープを用いた腎スキャン 97% (36/37)
- 造影CT 80% (12/15)
- 腎エコー 11%
鑑別診断
腎盂腎炎、腎結石が主たる鑑別となる。
- AFの既往は腎梗塞の確率を上げる
- CVA叩打痛は腎盂腎炎や腎結石を示唆する
- LDH上昇は腎梗塞を示唆する
- 血尿がなければ腎梗塞>腎結石、膿尿がなければ腎梗塞>腎盂腎炎
- 腎梗塞と腎盂腎炎の画像所見は類似するが、
- 造影CTで腎被膜に至る低吸収域、膿瘍→腎盂腎炎らしい
- Cortical rim sign→腎梗塞らしい(被膜下の腎皮質は側副血行により栄養)
初期対応
再灌流術の適応の有無をまずは判断する。造影CTで診断後、CTAを撮影し大動脈・腎動脈を評価する
- 造影CTで腎萎縮や濃い wedge-shaped scar がある場合は急性経過は否定的で、側副血行がある場合もあり、再灌流術のメリットが少ない。
- 再灌流術の利益があるかもしれない場合:
- 腎動脈の完全閉塞後6時間以内
- 片腎を栄養する腎動脈の完全閉塞
- 腎機能の有意な低下
- 主たる分節を栄養する動脈の閉塞から24時間以内
- 主たる分節を栄養する動脈が閉塞した例において、有意な腎機能低下があるか、高血圧の発症・増悪があるか、腹痛・血尿・発熱などの症状がある場合
- 大動脈解離が原因の場合
管理と治療
心エコー、モニター、血液検査などで塞栓の原因を検索する。
禁忌がなければ抗血栓薬を投与する。大動脈のプラークによる塞栓である場合は抗血小板薬が望ましいが、ほかの場合は原則として抗凝固薬を用いる。
初期にはヘパリン静脈投与とし、動脈造影・経皮的血栓除去の適応がなければワルファリン内服に移行する。腎機能を加味してDOACを初期に導入することは避け、安定期に入ってから考慮する。
参考文献
- 尿路結石等による痛み ↩︎
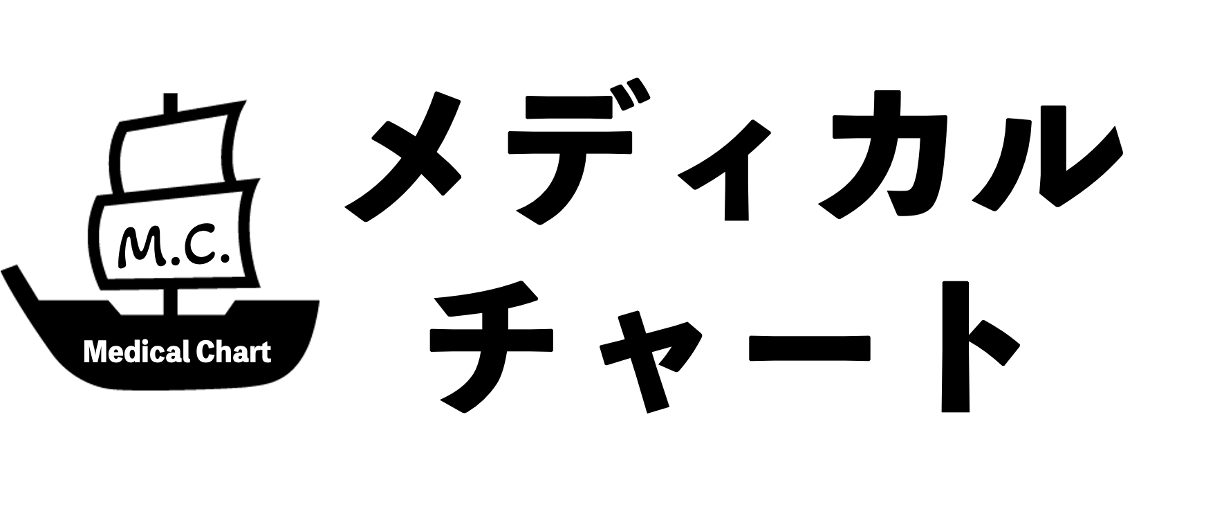

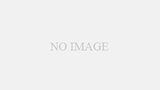
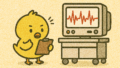
コメント